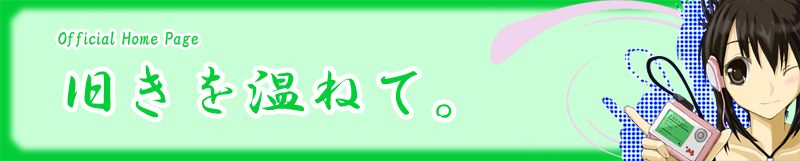






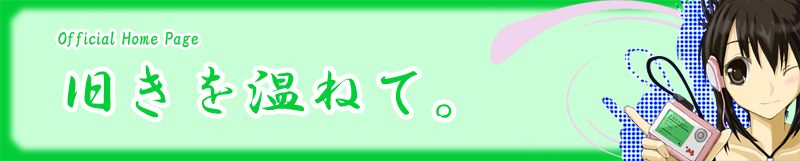 |
||||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
むかしむかし、硝子姫と呼ばれる少女がいました。 硝子姫は鏡に「この世で一番美しい」などといわれることはありませんでしたが、 笑った時の顔はそれはそれは可愛らしいものでした。 硝子姫は、もともと姫などというたいそうなものではなく、 ただの町娘に等しい存在でした。 ではなぜ硝子姫と呼ばれるのかというと、 彼女を白雪姫よりも美しいと、心から思う少年がいたからです。 一章 |
|||||||||||
本を閉じる。 人生で何度聴くことになるだろうか、そのパタンという音は、今が夏休みであり、帰路を歩いていることを思い出すにはじゅうぶんだった。 「子供達が愉しめる童話と大人が愉しめる童話の違いは、これでもかと美化されているか、現実志向なのかの差、かな」 いったいどれだけの人が、白雪姫は王子様のキスで起きたと本気で思っているのだろうか。実際は死んだ白雪姫を家来に運ばせている最中の事故で目覚めてしまっただけだというのに。 「死んだ白雪姫を運ばせて、お城でやましいことでもしようとしていたのかな? とんだ死体愛好家だ」 まあいいや。 翻訳家によって違ったふうに愉しめるグリム童話を鞄にしまい、深呼吸一つし、姿勢を正す。 怠け防止の中間登校も済ませたことだし、後は、なだらかに伸びる帰路を歩くだけだ。 登校は明日、明後日もあるので計三回となっている。とすると往復三回も、この土の固まったでこぼこの野道を蹴る乾いた音を聴くのか。 良くも悪くも田舎道。 汗でシャツが張り付くのが嫌で、襟元を振るって空気を入れる。 「風、吹かないかな」 思わずつぶやいてしまうほど、風に飢えた。 蝉(せみ)や蜩(ひぐらし)なんて暑さ倍増に拍車をかけるだけの厄介者だ。気分屋の風こそが夏の風物詩だと、僕は思う。 考えてもみれば昔からここ、久我市布野ヶ丘町にいるが、蝉におしっこをかけられたことさえ記憶に新しい。 たとえば今年が一九九九年七の月だとしても、僕は抽象的な予言なんかより、やっぱり熱中症のほうを恐れているだろう。 そんな現実的な自分を、浅ましくも、人間らしいなあと思う。
できることなら風になりたい。ふぅーでも、びゅーでも、音はどちらでも良い。あってないような存在になりたい。 だけど僕は、蝉や蜩だ。 なぞらえるならそんな季節感あふれる存在でなくてもいいかもしれないが、たとえばだ。蝉や蜩は無垢な子どもたちには可愛がられるが、大人には見向きもされない。生きていることは黙過されているが、それだけだ。暗い土の中で育って、やっと地上に出てきても鳴くことでしか自己主張できず、運が悪ければ子どもにバラバラに分解され、運が良くても墓を作ってもらうことすら叶わない。 僕は蝉。 ぼそりつぶやくと、どんなに哀れかが伝わってくる。 だから、本当に単純な信用が欲しかった。 僕は血の繋がった両親とさえ相互信用がとれていない。兄弟でもいれば、もしくは幼いころからたわいない遊び仲間を増やしておけば、小石を積み上げるように信用の塔を築けたかもしれない。 昔から――いまもそうだが、深い信頼関係を築けた例がなかった。燦々としたクラスの中でぽつんと浮いていることくらい自分でもわかる。 中島、カラオケのメンツが三人しかいないから来ない、とクラスの人に声を掛けられたとする。僕はすぐさま首を横に振るだろう。もとより、ついでのような呼び方が気にくわない。 これが、謙一カラオケ行かないか、後何人か誘ってさ、ならば僕の心の奥底にも光が射すだろう。そんな主役のような幸せな呼ばれ方、されたことはないけど。 次の日の中間登校も無難にすませた。明日もういちど登校すれば、夏休みは舞い戻ってくる。無難でなくなったのはそのあとの帰路のことだ。 遥か後方から「あれ、謙一」と僕を呼ぶ気安い声が届いたのだ。僕は振り返る。
特に、君みたいな人に必要だってことだ。 「……ねぇ、毎度毎度いうけど、あたしたち幼なじみなんだからもっとソフトなノリで話そうよ」幼なじみと名乗る彼女は、肩がこると付け足した。 「でも、昔から遊んでいれば幼なじみっていうのも、なんだか古典的で嫌なんだよ」僕は続けて言う。「僕のことが大切なのかどうか、それが大事だと思うよ、エミ」 幼なじみを自称するエミは間髪入れず、「大事に決まってるよ! そんなあたりまえなこと二度と聞かないで」と怒鳴った。 返答に窮した僕は、しかしわずかに表情筋を弛ませていたと思う。 空の色を映したような透き通る青。エミの髪は綺麗だった。 そのあとすぐにエミは帰ってしまった。友達と遊ぶために、いったん私服に着替えてから行くそうだ。 僕は帰宅すると、ベッドに転がって天井の蛍光灯を眺めていた。エミが言ったことは本心なのだろうか。本心ならば、僕の寿命があと一日だとしても受け入れる自信がある。それほど嬉しかった。 嬉し、い、嬉し、い、嬉、しい。変なリズムで、嬉しい嬉しいと薄暗い胸がヘンテコに躍る。 僕は一人きりの部屋で顔を綻ばせていた。その日は夜遅くまで目が冴えていた。 「よかったら、また一緒に帰らない?」勇気を出してエミに言ったのは、中間登校最終日だった。僕はあまり楽しくない表情をしていたに違いない。性分なのだ。 「うん、いいよ」エミはそれでも、曇りのない笑顔で返事をくれた。 そのときから帰宅途中までの僕は、見つかるはずのない忘れ物を取り戻したように願いの叶った顔をしていたに違いない。もちろん、心の変化がそのまま表情に張り付くのならばだけど。 「でさ、あいつがそのあとになんて言ったかわかる?」エミが楽しそうに話す会話はどれも、「正真正銘のバカだって、そう言ったの。く、あはは!」友達のことばかり。僕に関係した会話はひとつもなかった。 話し下手な自分が憎い。 ――ふいに幼なじみという口実を使って、どこかに行きたいと思った。二人で、どこでもいいから。 僕はたぶん、エミが信用できるのかを確かめたかったんだろう。 「ねえ、エミ。突然で悪いんだけど、今度どこか行かない?」なんださらっと言えるじゃないか、と我ながらに思う。 「え? えっと、ふたりで?」 その驚いた表情を見た瞬間だった。 氷さえも即座に溶かすような灼熱の岩――そんな圧倒的存在が、ドス黒い靄を漂わせて僕の中に入り込んできた。衝撃のあまり、反射的に目蓋を閉じる。 病気。危機。破壊。ただならぬ存在に脅かされる。 身体のどこかが壊れてしまったのだろうか。それならまだいい。そんな生易しくない。 四肢はブレーカーを切ったように微動だにせず、エミのことを半ば忘れかけていた。 どうしてだどうしてだどうして、だ。なにがどうしてだ。 駄目。無駄。 その存在はどうしても取り除くことはできない。紙切れを呑みこんだ両替機がジャラジャラと硬貨を吐き出すみたく、異物が流れ込んでは思考さえも塞いでいく。 やがて大きく形成された硬貨が、小作りな何かを形成した。 なんてことはない、鍵だった。
その強い気持ちは、異国に鎮座する錆びない鉄柱のように僕を支えてくれた。 「うーん……そうだなぁ」≪えー、謙一とデート?≫ 声が二つ聞こえた。空耳、幻聴、そう願う。 「今度っていつ?」≪まさか、あたし惚れられたのかな。適当にことわろ≫ 空耳じゃない。けど、この場合、空耳だと思うことはいけないのだろうか。 僕は時間にして三秒、口を開けて放心した。それが本音なんだと、全身で認めてしまったから。どちらもエミの声ではあったが、抑揚の違いは明らかだったのだ。 僕は病気にかかってしまったのか、という疑問が脳裏をよぎり、そんなわけがないと払い消していく。病気になる理由もないし、もとよりこんな症状、聞いたこともない。 「ね、ねえ、聞いてるの?」≪なによ謙一、急に変になっちゃって≫ もう一度瞳を閉じる。 鍵が抜け出していた。鍵は漆黒を纏ったまま、ゆらりと軌跡を残してエミの額めがけて向かっていく。 そして、 突き刺す。 ぶす、とかいう滑稽な音とともに。 「エミ!」 僕は驚いて瞳を開けるとともに、彼女の額に視線を投げる。 「な、なに!?」≪なんなの?≫ エミの額が錆びた鉄扉のように開き、そこから飛び出した情報が僕に流れ込んできた。
情報の群れは、一個一個、僕の脳に直接流れ込んでくる。 僕の、 僕の頭が、 パンクする。ぶぶぶぉぉぉぉぱぁんとパンクする。 やめろ、やめてくれ、 うるさい、うるさい、 うるさいうるさいうるさいうるさいうるさいうるさいうるさいうるさいうるさいうるさいうるさいうるさいうるさいうるさいうるさいうるさいうるさいうるさいうるさい! 戯言だと信じたい、虚言だと信じたい。 でも、これが現実のようだ。 蝉や蜩の鳴き声のような、人の本性の『鳴き声』が、僕には届くようになった。 鍵は、人の本音の扉を聞ける。ようやく手を伸ばしてチャンスをつかみとったのに、信用を攫っていってしまう盗賊のような鍵。 僕は膝をつくほど愕然としたが、家に帰るまでは平常心を装いたかった。 「なんでもないよ」嘘みたいに複雑な顔で、嘘みたいな言葉を、だから吐いた。 「そ、そう? あ、あたし用があるからそろそろ行くね。じゃね」≪早く帰ろっと≫ 「待って」 でも。 人を信じられない僕は、鍵さえも疑った。 自分だけが頼り。もしかしたら、この鍵は僕の空想なんじゃないか。エミは僕のことをこころよく思っているのではないか。 それを聞かないと、明日から再開する夏休みの間――いや、一生かもしれない――絶対に後悔する。だから、最後の望みに賭けた。 「ねぇ、エミ。君にとって僕はどんな人なんだ?」 「大切な幼なじみ、大切な友達だよ。じゃね」≪考えたこともなかった。どうでもいいや≫ ぐらぐらがらがらがら、となにもかもがくずれていく音が聞こえた。 終わったと思った。 エミの足音が消えたころ、いつもよりスピードを落として帰宅した。その間、考えたのはたった三分だけだった。 もしかしたら僕は鍵の登場には薄々気づいていたのかもしれない。 幼児から少年へ、少年から青年へ成長を遂げる過程で、鍵という存在はすぐそこにあったのだろう。エミなら信用できるかも、という希望の兆しが発現の一押しになっただけで、すぐそばに隠れていたのだ。 超能力とか、その類だろうか。 まったくいらないんだなこういう能力って、というのが冷静になってたどり着いた第一の感想。 だけど、第二の感想はまったく逆だった。 ――これはチャンスではないだろうか、という感想。 動悸が著しい激しさをみせる。爆竹のように心臓に負担を掛けていく。 「この鍵を使えば、もしかして」 信用してもいいかもしれない、と思えたエミに裏切られたこの状況。打破すべき状況。 僕を信用してくれる人は、残り二人だけなのだ。 開けてみよう。残り二人の本性も曝け出してしまおう。 そして、僕は大声で笑うだろう。 ――ああ、笑うぞ、僕は。 「父さんと母さんの扉も開けてやる。世の中に絶対的信用はないってことを証明してやる」 本当は信用を求めているのに、僕は自虐的にもそんな発言をしつつ凪いだ野草を踏み潰した。くしゃり。
二階に位置する部屋の特権は、ベランダに出て月を眺められることだ。夜も十時になるとベランダに出て、お気に入りのジャズピアノを月に向けて流しながらリラックス。それが日課だった。 なのにどうだ。 こんなにも俯き加減では、視界には見慣れた住宅地しか映らない。これでは、月ではなく信用のない人たちへ送る、ジャズピアノの甘美なメロディラインになってしまう。 さきほど僕は、愛すべき両親の顔を見た。一階の居間で、楽しそうに温泉旅行の計画をたてていたのだ。所要人数は二人のようだ。 ああいいさ、父さんも母さんも好きにすればいい。どこへでも行けばいい。そのまま帰ってくるな。 びゅう、と夏の風が吹いた。それは僕の手を取って、一瞬で現実に引き戻してくれる。 そうなのだ。 僕には風があった。 風は、優しく元気づけるように吹くときもあれば、怒って追い出すような突風のときもある。人より、よっぽど感情が豊かだ。 そういう意味では、風も僕も似たり寄ったりかもしれない。 含み笑い、そして嘲笑。 「大笑いしてやろうって、そう思っていたのに、結局は中途半端に笑って、……笑って、それで終わりか」 なあよう。 どこに行けば信用は手に入るんだ。 風になれるんだ。 答えを教えて欲しくて、無意識にベランダに手をかけた。 ――もしかしたら、 ここから跳べば――飛べば、風になれるのかもしれない。 「根拠がない――」 根拠。真理。存在に帰結するための絶対要素。 待てよなんだそれ。 自身を否定までして、すがるべきものだっただろうか。 「いらない。理屈じゃない」 馬鹿馬鹿しくなるほど、僕の決心は固まっていたようだ。 金城湯池の信念を胸に、まったく助走のない、格好悪い形で身を投げていた。 下は見ず、月を睨んで高みを目指す。 落ちない。 理屈じゃない。 これが、これが風。 落ちない。 時間の概念を忘れてしまう。もとい、僕という概念の消失。 その空間の中、僕は自分が風になったことを認めた。風という概念の誕生。 それは一時的なことで、恒久的なものではないと思う。 愉悦。恍惚。陶酔。 そうだ、指を動か
夜目が庭に咲く雑草を瞬間的に追い、右足が異様な角度で土にめり込んだ。軸足を取られてなすすべもなく重力に屈し、身体がバラバラになるほどの衝撃で叩きつけられた。 ああそうか僕は落ちたんだ、なんて思う間もなかった。
その後二日間は自宅療養を行うことになった。 あのときは地面に叩きつけられたことによる痛みよりも、風になったことを誰でもいいから伝えたかった。庭に生えた樹のような僕が大笑いしているのを見た両親は、閉口せざるをえなかった。 穏当な理由もなくベランダから飛び降りる――一応、事故ということにはしたが――客観的に考えても、気に触れたと思われたに違いない。 だが、どうでもいい。僕はもう、蝉や蜩のような存在ではないのだから。僕はあの一瞬だけでも風になったのだから。 低俗な昆虫類は、鍵で暴けばいい。それでいい。 四角いベッドの上で、ジャズピアノが優雅に流れる。その調べは、何もないこの部屋に反響し、ゆとりを持たせた。 心地いい。 思考を中断して、曲の終わりを待った。ゆっくりと余韻を残してフェードアウトしていくピアノラインを聞きながら、 「日本の人口は一億を超える。僕はその中の一人に過ぎず、その中の十万分の一ほどにしか会っていない」 口にしたのは、天井の模様を仰視しながらだった。 両親や幼なじみに裏切られたから、なんだっていうのだろう。確立の上では、信用できる人はまだまだたくさんいる。 信用。 それだけを考えて一日を過ごすことがあるくらいの僕だけど、その言葉を辞書で引いたことはなかった。すぐ取れるよう枕元に置いてある辞書の〝信用〟の欄がある頁は破り、ゴミ箱へ、ゴミ収集車へ、焼却という結果に向かって走る。 だが、もう調べてもいいのだ。十七年間――特に最近は夜も眠れないほど悩ましいキーワードだった〝信用〟を調べてもいいのだ。 瞳を閉じて明日に備えると、曲の節目で意識は途絶えた。 午前十時。 図書館への所要時間は徒歩で三十分足らずだった。駅の方角に歩いて行くと、僕の住む久我市と都市化の進みつつある相良原市の境がある。それを越えて大きな道路まで出たら、後は道なりに歩くだけ。到着の前に、自動販売機でオレンジジュースを飲んだ。爽やかな飲み心地を提供してほしかった僕は、一〇〇%という文字に渋面し、ちっと舌打ちして完敗を表した。 図書館の外観は、青と白の大きな台形の右上を折ったようだった。駐車場の埋まり具合は上々だったが、ちょうど降りてきた家族が逆方向に歩いて行くのを眼で追えば、隣の公園に向かって行く。ちらほらと同様の出入りも含めると、図書館はそれほど込んでいないのかもしれない。 返却ポストに、借りていたグリム童話を放り込むと、図書館に入った。 本の匂いは、『高級な埃』そんな表現がしっくりくる。子供の声がまれに聞こえるていどの室内も、安らぎのツボをピンポイントで押してくる。 知恵の宝庫とは、よく言ったものだ。 深呼吸を三度し、辞書と信用に関する資料を何冊か見繕おうとして書庫を歩いて行く。辞書を見つけると、感情を抑えきれなくなってその場で開いた。 『――信用 一、 人の言動や物事を間違いないとして、受け入れること 二、 間違いないとして受け入れられる、人や物事のもつ価値や評判』 重い息と同時に、パタンと本を閉じた。 予測していた答えだった。やはり、世俗的な答えでは、僕は納得できない。 信用の本は――心理学の分野だろうか。書庫を歩き、探していく。 窓際を見る。規則正しくならぶ三人掛けのソファーには暗黙の了解のようなものがあるようだ。真ん中を残して、角と角、二人が座っているのだ。電車の中などで他人同士が密接しない為に行うのと一緒だな、と思った。 ああいうのも、ちょっとした信用なのだろうか。 苦笑とともに稚拙な考えを破棄し、本を求めて歩こうとしたところで、僕は抑揚の高いすっとんきょうな声を上げてしまった。 数人が視線を向けたが、彼らの不思議そうな視線を僕に向けるのはお門違いだ。そう、ソファーの方に向けるべきなのだ。 そこに、ぴょこぴょこ飛び跳ねる少女がいた。その風采は奇妙奇天烈極まりないものだった。 姉のお下がりのような、体系に不一致の大きな、そしてピンク色のダッフルコート。髪型とか、顔とかそんなことどうでもよかった。この暑い夏に、大きな、冬着を、堂々と、着ている。それだけが事実だった。 少女は本棚だけの視界から消え去った。すぐさま追うと、ソファーに座る高校生ほどの男のそばに立ち、小首をワイパーのようにせわしなく動かしている。 ――本を見ている? なんだ、彼氏といるのか。あの特異な出で立ちは流行りだろうか。よくわからないが、館内ならクーラーも利いているし、変ではないのかもしれない。流行にうとい僕が悪いのだろう。 気を取り直して、書庫を歩く。探した結果、意外にも経済関連の本に信用についてのことが表記されているようだった。 なんとなく、気が進まない。 悪い意味で適当に本を取り、ソファーに向かう。困ったことに空きがなかった。はばかるものでもないし、さっきのカップルの席――その角に腰掛けた。 第一声を聞いたときは、うんともすんとも思わなかった。 「ひさしぶりに見る顔だなぁ。今日は、『クレジットと信用の相互性』かぁ。へぇ、相変わらず難しい本読むんだなぁ」 ダッフルコートの少女は、口元を猫のように緩ませて言った。 誰に。僕に。まさかまさか。 「むふふ、大人ぶってるなぁ。図書館で、周りの人に自分が難しい本を読んでいることを褒めてほしいとかぁ――」少しの羞恥心もなく、僕を上から覗き見て、「――もしくは、涼みに来ただけなんだけど、それじゃカッコ悪いからこの本で隠しているとか、なーんて、きゃはは!」 好き放題しゃべって、大声で笑った。 憤慨という言葉が爆発する。 こういった有象無象は、笑うべき場面でもなく、所在無ささえも感じないかん違いをする。 僕は彼氏を思い切り睨みつけた。それに気づいた彼氏が驚いた様子でどこかへ消えた。少女にも一瞥をくれると、それで満足した僕は本に目線を戻した。これでいい。 「え……うそ……いま、見たよね?」 なぜか少女は、まだそこにいた。僕は目もくれず、無視する。 「ねぇ、見たよね。仔乃乃を見たでしょ?」 無視。 「ねぇ、ねぇってば、ねぇねぇねぇ」 無視。 「仔乃乃が見えたんでしょ? ねぇ、ねぇねぇ、ねぇってば!」 うるさいな、けど無視。 「……いいよ、わかった。じゃあこうするしかないよね……すぅ」 少女は深呼吸をして、 「あぁあぁああああああああああああああああ!」 図書館で、図書館で、図書館で――叫、叫ぶ。女特有の甲高い声が館内に響く。 僕は本をデタラメなくらい乱暴に床に叩きつけ、威嚇とともに、顔を近づけていた。 ふざけやがってふざけやがってふざけやがって。 「なんだっていうんだ、僕になんの用がある。いいかげんにしてくれ!」 「あ……あは、あはは」 少女は幽霊にでも会ったような顔で驚いたあと、笑った。 どうかされましたか、と司書の方が来てくれて、僕は事情を説明する。 「どうもこうもないですよ。彼女が、あああって叫んだの聞いたでしょう?」 なにも飛躍的ではなく、ありのままの事実だ。 「声、彼女……え、あの、どの子でしょうか」 「あなた、目が見えないのか? そんなので、本当に司書の資格を持っているのか不思議だね」司書もどきを揶揄する。 「どの子でしょうか?」 「だから、ほら、ここ! 夏なのにコートなんて着ている、この子! どれだけ説明させる気なんだ」 人に対してこんなに熱くなったのは久しぶりだ。目立ちたくもないのに、なんでこんな状況になったのだろう。 そんな想念を断ち切ると同時、頭の後ろで手を組んでにんまりと笑う少女を指差す。こんなときにまで笑っている――ふざけるにもほどがある。 「あの、失礼ですが、どこにいるのでしょうか?」 司書は司書で、まったく話にならない。 「らちが明かないな。あとは僕にまかせて、その盲目で読書でもすればいい」 自分の力でどうにかするからどこかへ行け。 僕は少女の手をつかもうと手を伸ばす。 空振り。 バランスを崩して倒れそうになった僕が真っ先に考えたのは、単純な疑問だった。 なぜ? 確かにコートの袖に触れたはず。なのに五感すべてが拒絶を示したように、そのまま空虚をつかむだけだった。 外れた? いや、そうではない。そうではないんだ。 そこには何もなかった。同じ空気が存在しているだけだったのだ。 「あは……仔乃乃は、幽霊だぞぉ」 ちょっと整理したい。というかもう本当にやめてくれ冗談じゃない。 「あの、大丈夫でしょうか?」司書が介入してくる。 「ごめん。もう大丈夫だから、騒いだりしてすいませんでした」 きちんと謝ると、司書の方はなんども僕を心配した後、最後に簡単な注意をして戻っていった。有能な司書だったようだ。 「えへ、よいしょっと。とーなり、もーらい」言いながらソファーに跳び、ぽすん、と音が――しなかった。 着地音がない――つまり、幽霊。 驚いた。驚いたが、〝鍵〟よりは幾分マシな話だ。 なにせ自分には関係のないことだから。 僕は外に向かった。 「あれ? ね、ねぇねぇねぇ、どこに行くの?」 ここにいる意味も、価値も、忘却。 「ねぇねぇ、いつも来てた人でしょ? 知ってる知ってる、仔乃乃はきみのこと知ってるよ」 無視。 「でも、幽霊の仔乃乃のほうが驚いちゃった。だって、前に来てたときは見えてないと思ってたんだもん」 「最近、見えるようになったのかも」しかたなく小声で返信すると、少女は嬉しそうに飛び跳ねた。 「そお! よかった。ね、ねぇねぇ、帰っちゃうの、かなぁ。明日も来るよね?」 「もう来ない」 自動ドアを抜け、外に出た。さらに歩いて行くと、図書館からだいたい五メートルほどまで少女はついてきたが、「待って!」 その声で、僕は振り向いた。 少女らしい、両手を胸の前で組んで、懇願するような瞳。 「そこから先には来られないんだね」思ったことを、ただ口にした。 「そ、そうだよ。この図書館から十歩くらいのところには行けないの。ねぇ、おねがい、明日も来てくれるんだよね? ね」 少女の腰まで伸びた茶色い髪に、白昼の陽光は反射しなかった。白い足、コート、髪にも影はなかった。 「あれだけ恥ずかしいことになったんだ。あえて来ようとは思わないだろ、誰も」 「そんなの、仔乃乃はぜんぜんかまわないよ? だから、明日からは一緒にあそぼ」一呼吸おいて、「おねがいだよ……」少女は言った。 悲痛な声色だった。 その声は、たとえばドキュメンタリードラマで生き別れた兄弟が再会した、くらいの情緒で発せられるものではなかった。断じてなかった。 「ねぇ、おねがい……」 震えた声だった。 僕に伝染した。僕も震えた。 足が地面に張り付いて、動かなかった。 そのまま、ぶるぶる震えていた。 孤独、その意味で少女と僕は同じだ。 信用、その意味で少女は一筋の光だ。 おいちょっと待て、本当に同じだろうか。 ――鍵。 そうだ、鍵を使ってみればいい。 「……おねがい……仔乃乃ね……ずっと独りだったんだもん……」 少女の涙。 必要としている。 僕を、中島謙一を求めている。 いらない。鍵なんていらない。 唇を噛んだ。うすい鉄の味が咽喉を抜ける。 なあおい。この少女こそ、求め続けた『信用の形』じゃないのか。 欲しい。欲しいよ、信用が。 「おねがい……おねがい……」 もう駄目になっていた。少女が消えてしまわないかと本気で不安になった。 求めた。走った。風になった。最短距離を走り抜けていた。 少女を眼前に見据えて、僕は、ようやく、一切の作りをせず、笑った。 こぼれんばかりの笑顔が、こんなにも近くにある |
| BACK |